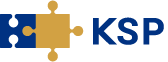せどりをしていると利益が大きくなってきたので、会社を設立したいと思っている人も多いのではないでしょうか。
実際に、コロナ禍になってからは、せどりなどの副業が人気になり、せどりで利益を上げられた人の中には法人を設立しようと考えて、法人を設立されている方も多いです。
そこでこの記事では、せどりで会社設立する際のメリット・デメリットや古物商許可証について紹介していきます。
せどりで会社を設立する3つのメリット
せどりで会社を設立することのメリットは、以下の3つです。
- 1.銀行からの融資を得やすい
- 2.対外的な信用度が高まる
- 3.経費にできる項目が多くなる
それでは、詳しく見ていきましょう。
銀行からの融資を得やすい
せどりで会社設立することで、銀行からの融資が受けやすくなるというメリットがあります。
もちろん、法人を設立したからと言って、銀行から無条件で融資を受けられるわけではありません。
しかし、銀行は法人の信用度を見ている部分が大きく、会社として利益を上げることができていれば、その実績を元にお金を借りやすくなるのも事実です。
また、個人事業主で同じ利益率や収益を誇っていたとしても、個人という不安定性から融資を受けられないこともあります。
そのほかにも、法人として会社を設立することで、創業融資などが受けやすくなります。
創業融資とは、創業の際に受けられる融資のことです。
日本政策金融公庫などの政府系の金融機関や民間の金融機関でも実施しており、お金を借りやすくなるという特徴があります。
このような制度を使うことで、銀行からの融資を受けられやすくなるのもメリットでしょう。
銀行からの融資を受けて手元の資金を大きくすることは、せどりでは非常に重要なことです。
せどりでは、まず手元に資金がないと商品を仕入れることができず、いくら手元にあるかによって、どのくらい利益を上げられるかが異なってきます。
そのため、最初は銀行から多くのお金を借りた上で、商品を仕入れて転売していくという方式をとったほうがいいでしょう。
対外的な信用度が高まる
せどりで会社設立することで、対外的な信用度が高まるのも1つのメリットです。
例えば、せどりだけではなくてせどりセミナーと称して、これからせどりをやってみたいと思っている会社員の方に対してセミナーを実施する事業を展開するとします。
この際には、もちろんどのくらいの利益を上げていて、どのくらいのお金を持っているのかという実績の部分も重要ですが、セミナーとして人を集めるためには、法人か個人事業主かも重要なポイントです。
一般的な感覚として、法人として独立されている人は、社会的な信用度も高く何か話している時でも、「信用できるな」と思われる可能性が高いでしょう。
もちろん、個人事業主の場合も信用できない訳ではありません。
しかし、個人事業主という形はまだ一般にはそこまで周知されていない存在であり、肩書きでは信用を得られない可能性もあります。
そのため、セミナー事業などを展開したい場合は、会社を設立をして株式会社〇〇という形で、セミナーを打てるようになると集客力も上がるでしょう。
経費にできる項目が多くなる
せどりで会社設立することで、経費にできる項目が多くなります。
法人になることで、家族への給料も経費にすることが可能です。
また、法人の場合は家族への給料のみではなく、自分への給料も経費として計上することができます。
そのほかにも、社宅として会社が家賃を補助する制度がある場合、社宅として経費にすることが可能ですし、自分自身に対して車を買った時に会社で購入したことにして、業務で移動手段として使うのであれば経費として認められる可能性が高いです。
このように、個人事業主では経費で落とすようなことができないものであっても、会社を設立して法人になることで経費で落とせる可能性があります。
ただし、ここで注意して欲しいのが経費で落とせるのは、あくまでも事業に関連するものだけであるということです。
例えば、社宅費用などは直接事業には関係ないように思えますが、社員に対しての福利厚生の一環としては重要なものです。
そして、会社を設立した代表者も社員になります。そのため、代表者が自分自身に対して家賃補助を出している場合は、その家賃補助を経費として落とすことができます。
しかし、無償やあまりに低い家賃で社長に貸し付けてしまうと、かえって社長に多く課税されてしまうリスクがあるので注意してください。
ただし、会社を設立することで福利厚生など社員のために必要なものに対しても、経費で計上できるようになるのはやはり大きなメリットでしょう。
せどりで会社を設立する3つのデメリット
せどりで会社を設立するデメリットは、以下の3つです。
- 1.設立にお金がかかる
- 2.事務処理が多くなる
- 3.法人維持コストがかかる
設立にお金がかかる
法人を設立する際には、税金などの法定費用がかかります。
株式会社の場合は、定款を認証してもらうために5万円、株式会社を設立するための登記費用として法務局に15万円支払う必要があります。
そのため、株式会社を設立するためには最低でも20万円はかかることを意識しておきましょう。
一方で、合同会社の場合は定款の認証が不要で、登録免許税も6万円なので、株式会社の半分以下のコストで法人化することが可能です。
法人化の際には、経営サポートプラスアルファにご相談いただくことで、経営者様の将来的な方針などをもとに最適な提案をさせていただきます。
また、経営サポートプラスアルファでは株式会社・合同会社ともに法人化の際に、法定費用以外の代行手数料などは0円で対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
事務処理が多くなる
会社設立することで、事務処理が多くなります。
社員を雇っている場合は、給料の計算が必要になりますし、その他にも細々とした経費の精算なども必要でしょう。
会社内で経理を設けて、帳簿作成しなくてはいけないこともありますし、社会保険料の支払いなどの事務処理も多くなります。
もちろん社員との事務処理が多くなるだけではなくて、国や関係省庁などに法人として支払わなくてはいけないものに対して、支払い先との連携も多くなります。
ただし、一人で会社を設立する場合は、概ね個人事業主と変わらないくらいの事務処理で終わることが多いです。
また、複数人の社員を雇う場合でも、経理や事務処理専門の社員を雇うことで、代表者にかかる事務処理の負担は大幅に抑えることができるでしょう。
一方で、経理や事務処理専門の社員を雇うだけでもお金がかかるのは事実なので、コストとパフォーマンスの関係を重視しながら見極めるといいです。
法人維持コストがかかる
法人を維持するためにはコストがかかります。
維持するためには、法人住民税や法人所得税など法人にかかる税金を支払うだけではなく、税理士への顧問料も必要です。
しかし、顧問税理士を雇うことで、正確な会計処理や税金計算のみならず、様々な節税対策を提案してもらえます。
もちろん、会社の中だけで税金の処理をすることはできます。
しかし、そもそも経費に計上できるものか、できないものかの判断や事業スキームが税金の観点から問題ないものであるのかなどは、代表者だけでは判断できず税理士など会計に関しての専門的な知識がある人でないと判断が難しいのが事実です。
そのため、90%以上の会社が税理士をつけています。
会社を設立すると古物商許可証は再取得?
事業としてせどりを展開していく際には、古物商許可証が必要になります。
古物商許可証は、個人事業主でも取得することができ、個人事業主であってもせどりを事業として展開していく際には古物商許可証が必要です。
このような背景から、個人事業主から法人になった場合、古物商許可証を代表者が既に取得している場合があります。
しかし、結論から言うと古物商許可証は会社設立すれば再度取得しなくてはいけません。
これは、古物商許可証はあくまでも個人事業者の場合は個人に対して与えられたものであって、法人に対して与えられたものではないからです。
そのため、会社を設立して法人として古物商許可証が必要なせどりを行っていく場合には、古物商許可証を取得しておく必要があります。
せどりで会社設立する基準とは?
せどりで会社設立する基準がわからないと思っている人も多いでしょう。
実際に世の中で、会社を設立した方がいい基準は様々あり、800万円や500万円などと言われることが多いです。
ただし、結論から言うと1000万円という基準で考えるのが一番いいでしょう。
この1000万円は年収ではなく年商1000万円です。
年商1000万になると、消費税の支払いが必須になります。
ただし、資本金1000万円以下の会社は設立後1年間は、消費税の支払いが免除され、設立から半年で売り上げが1000万円未満の場合は、設立後2年間は消費税の支払いが免除されるという制度があります。
消費税は10%なので、これを支払うか支払わないかは大きな問題になるのが事実です。
そのため、個人事業主から法人になる人は、個人事業主として年商1000万円を数年間達成した上で、消費税の支払額が大きくなってきたところで法人を設立して、消費税の支払いを免除してもらうという形が多くなっています。
まとめ
せどりで会社を設立する場合も、他の事業で会社を設立する場合とほとんど変わらず会社を設立することができます。
また、せどりで会社を設立する際には、経営サポートプラスアルファにご相談いただくことでスムーズに会社を設立できるだけではなく、創業の際に受けられる融資や助成金の情報などを提供させていただくことも可能です。